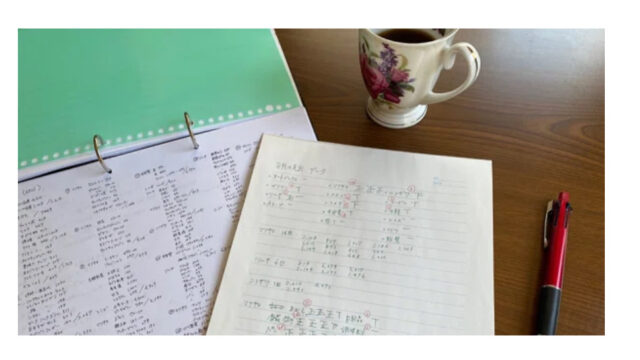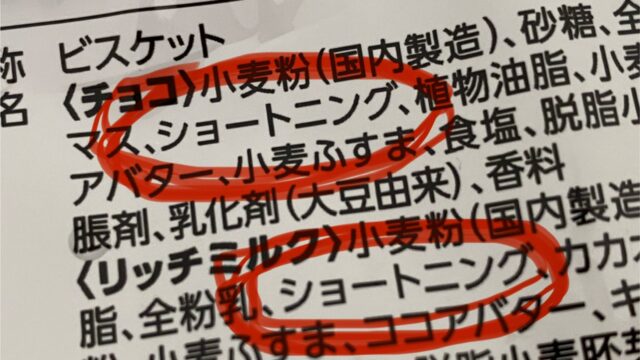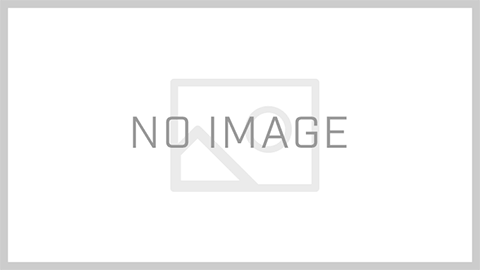〖エイサー検定3級・2級レベル〗沖縄伝統芸能の《エイサー》の基本的知識をまとめてみた!

こんにちは!専業主夫の直です。
初めてのエイサー検定を受けてみたい!
という方に向けて。
過去に夫婦で沖縄移住していた私が、
『沖縄の伝統芸能エイサーのことをもっと知りたい!』
と思い、調べていくうちにエイサー検定に行きつきました。
本記事は〖エイサー検定3級〜2級〗範囲の内容を簡潔にまとめたものです。
ネット等で勉強しながら、知識を補足してきました。
基本的な知識になっていますので、エイサーの基礎から知りたい方のお役に立てれば幸いです!
(アイキャッチ画像は沖縄市全島エイサーまつりの様子です)
Contents
エイサーとは?
エイサーとは、
沖縄の旧盆(旧暦7月13日~15日)に、各地域の青年会が中心となって踊る伝統芸能である。
お盆に返ってくるご先祖様の霊を供養し、再びあの世へお送りするために踊るということ。
エイサーの起源
念仏踊り(ねんぶつおどり)
起源は、琉球王朝時代、
《京都の僧侶:袋中上人》が沖縄に伝えた念仏踊りにあるとされている。
袋中上人(たいちゅうしょうにん)は、江戸時代前期の浄土宗の学僧。
沖縄に初めて浄土宗の念仏を伝え、琉球の伝統芸能であるエイサーのルーツとなった踊念仏を広めたことで知られる。
組踊り
元々は各地の念仏踊りが地域ごとに独自に発展。
そこへ組踊りの形式を取り入れて現在のエイサーになった。
エイサーの構成要素④つ
①太鼓
踊りの中心となる太鼓には、主に大太鼓、締太鼓、パーランクーの3種類がある。
大太鼓:力強い低音で全体を支える。
締太鼓とパーランクー:軽快な高音でリズムを刻む。
②地謡(じうた)
歌と三線で構成される音楽隊のこと。
地謡がエイサーの演舞をリードして盛り上げる。
③旗頭(はたがしら)
巨大な旗を操り、隊列の先頭でその青年会の「顔」となる。
④チョンダラー
顔を白く塗った道化役のこと。
場を盛り上げたり、踊り手の隊列を整えたりする重要な役割を担う。
エイサーの種類
エイサーは地域ごとに異なるスタイルがあり、「○○型」と呼ばれている。
◇沖縄市型
太鼓を力強く叩き、勇敢な演舞が特徴。
◇具志川型
女性の踊り手が中心で、優雅でしなやかな動きが特徴。
◇読谷型
躍動感あふれる太鼓の動きと、華やかな衣装が特徴。
エイサーの演舞形態
⭐︎道ジュネ―
お盆の夜に、集落の道を練り歩きながら踊る伝統的なスタイル。
⭐︎演舞場
地域の広場や特設会場で行われるスタイル。
じっくちと観客に見せるための演舞。
現代のエイサー
✔︎創作エイサー
伝統的なエイサーに加えて、現代音楽や新しい振り付けを取り入れたもの。
✔︎全島エイサーまつり
毎年沖縄市で行われている、沖縄県最大規模のエイサーイベント。
全国や世界各地から多くの観客が集まることで知られている。
おわりに
以上がエイサー検定3級~2級の知識レベルということです。
学びになりましたでしょうか?
沖縄が好きで沖縄の文化のことをもっと知りたい!
エイサー検定1級に挑戦したい!
という方はこちらの記事も参考にしてみてください(´ω`*)
〖エイサー検定1級レベルの知識編〗沖縄移住歴のある私がエイサーについて学び直してみた